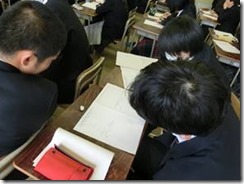サイエンスチャレンジ岡山2018に参加しました
2018年11月19日
11月10日(土) 吉備路アリーナを会場に「サイエンスチャレンジ岡山2018」が開催され,本校から1年生6名,2年生7名が参加しました。

開会式 いつものアリーナがコンテスト用に整備されていてびっくり。初めて参加する1年生からは思わず歓声が上がりました。

筆記競技 数学・理科・情報などに関わる多分野から総合的な問題が出題。骨のある問題ばかり。
1年生「問題自体が理解できません!」

2年生 「1年生にはわからんわ。そのうち習うよ。」~近い将来理解できる自分になることを楽しみにする1年生たちなのでした。~
実技競技① 化学・物理分野


「自作探査機『はやぶさ3』に見立てたコルク栓を小惑星『モモタロウ』に見立てた的に軟着陸せよ」という競技。化学と物理の知識を融合してミッションを遂行できるか!?
実技競技② 生物・地学分野
「吉備路フィールドワーク」
「問題:煮干しから耳石を取り
出せ」 ・・・ええっ!


さて耳石はどこにあるでしょう。
実技競技③ 工学分野
「ポリエチレンチャレンジ」
養生シートとストローを使ってヨットカー・飛行機・熱気球を製作。その性能を競う。かなり自信のあった熱気球が天井に舞うハプニングが・・・。

前日までの準備段階でうまくいっていたものが思い通りにならず,自信のなかったものが案外良い結果になったり。その都度立ち止まりメンバーと相談し,考え,進んでいく。まさに 理数の醍醐味を味わった一日でした。
<チャレンジャーたちの感想(一部抜粋)>
・来年理科で習うのが楽しみになり,モチベーションが上がった。(1年)
・頭を抱える問題ばかりでしたが,また参加したいです。(1年)
・今回のサイエンスチャレンジで理系分野の興味が広がった。
後輩にも頑張って欲しい。(2年)
・わからない問題は人と話し合って解決することが一番理解が深まる。勉強する上で大切なことだと知った。(2年)
サイエンスチャレンジ前日
2018年11月9日
11月9日の放課後、
明日のサイエンスチャレンジに向けて最終打ち合わせをしています。
複数の課題の試作品をいくつも作りました。
実験もしました。レポートも書きました。筆記試験の勉強もしました。
理数に興味がある2年生チーム(7名)と1年生チーム(6名)が参加します!
大会当日の様子をまた理数系のページでお知らせします。
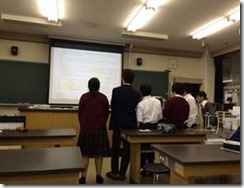
![clip_image002[4] clip_image002[4]](http://www.sojam.okayama-c.ed.jp/wordpress/wp-content/uploads/2018/11/clip_image0024.jpg)
遅くまで残ってまだまだ活動しています!
![clip_image002[6] clip_image002[6]](http://www.sojam.okayama-c.ed.jp/wordpress/wp-content/uploads/2018/11/clip_image0026.jpg)
2年生理数系県立大学にいってきました
2018年09月20日
9月19日(水)午後
2年理数系高大連携事業で
岡山県立大学情報工学部を訪問しました。
学食体験、全体説明後
6つのテーマに分かれて貴重な実験体験をし、
有意義な時間を過ごすことができました。

類型HPと通信「理数の窓」で
詳しく報告させて頂く予定です。
理数の窓が発刊されました!今年度創刊号
2018年04月19日
理数系の通信が発刊されました。
1年生の皆さん、理数系も面白いよ。
PDF からどうぞ
理数の窓創刊号
平成29年度 理数講演会(後期)
2017年12月20日
平成29年度 理数講演会(後期)
日時 平成29年12月13日(水) 6・7時間目
場所 視聴覚教室
対象 理数系:2学年1・2組(82名)
講師 岡山大学大学院教育学研究科 中川征樹 准教授
題目 「牛一頭分の皮で覆える土地の大きさは? -ディドー(Dido)の問題-」

ディドーの問題には、歴史的な背景があります。 紀元前6世紀頃に地中海貿易で栄えた古代都市国家「カルタゴ(Carthago、 Carthage)」(現在のチュニジア共和国の首都チュニス近郊にありました)は、 紀元前814年にフェニキア人(Phoenicia、 Poeni)によって建国されたと言われています。 その建国にあたっては、 次のような伝説が残されています。
地中海東岸の都市国家ティルス(テュロス)(現在はレバノンの都市スール)の国王の娘であったエリッサは、 国王の弟である叔父のシュカイオスと結婚し、 巫女として神に仕えていました。 その後、 国王である父が死去し、エリッサとその兄ピュグマリオンは、 父の遺言に従って、 共同で国を治めることになりました。 ところが、 兄ピュグマリオンは、 王位を独占しようと企み、 エリッサの夫であるシュカイオスを殺害し、エリッサの命をも狙いました。 そこで、 エリッサは家臣を従えて、 海へと逃がれました。 長い航海の旅を続けるうちに、 エリッサは「ディドー(Dido) (迷える人)」と呼ばれるようになりました。 長旅の末、 ディドーとその家臣の一行は北アフリカ沿岸の岬に辿り着きました。 ディドーは、 その土地が気に入り、 そこに国を作ろうと考え、 その土地一体の支配者であるイアルバース(ヤルバス、 ジャーバス)に、 土地を分けてもらうよう申し入れました。 ところが、イアルバースは、 この申し入れに難色を示し、
「牛一頭分の皮で覆えるだけの土地であれば分け与えてもよい」
と言いました。 「牛一頭分の皮で覆える土地・・・」。 そんなところに国を作ることなどできようか? ディドーは途方に暮れます。 と、 そのとき、 家臣の一人(きっと、 その人は数学が得意だったのでしょう)が妙案を思い着きます。 新しくできあがった町はフェニキア語で「カルト・ハダシュト(Kart Hadasht、 新しい町)と呼ばれ、 これが後にラテン語で「カルタゴ(Carthago)」と呼ばれるようになりました。
このような歴史的背景を導入に、ディドーの問題について、講義をいただきました。先生の講義のみならず、演習問題も用意していただき、生徒は四苦八苦しながら相互に教え合う姿もみられました。
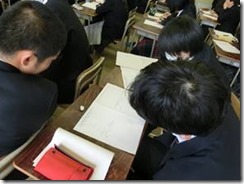
<生徒感想>
・「長さが決まったひもで、どのように囲めば面積が一番大きくなるか。」という一瞬簡単そうと思わせる問題だったけど、それを証明するのはとても難しく、逆に、頭を柔らかくすれば、中学生・小学生でも簡単に証明できることが分かり、数学の奥深さに感激しました。
・一つひとつは今まで習ってきた内容で、それを上手く使うことで、色んなことを数学で証明できるのはとても役に立つと思いました。
・難しい問題を出されて解けないと思っていたが、解説を聞いてみると、意外と知っていることの応用だったのでびっくりした。

サイエンスチャレンジ岡山2017に出場しました。
2017年12月4日
サイエンスチャレンジ岡山2017に出場しました。
11月18日 吉備路アリーナを会場にサイエンスチャレンジ岡山2017が開催され,本校から1年生8人が出場しました。


当日はあいにくの雨。筆記試験が終わり化学実験と平行して行われたフィールドワーク(生物・地学分野)で
野外に出る時には雨が上がり,野外に設けられた問題を求めて3人1組で走り回りました。


最後は工学分野。割り箸と輪ゴムを使って射的装置・投的装置・車を作りました。


残念ながら入賞はできませんでしたが,「来年もチャレンジしたい!」という気持ちが生まれた1日でした。
最後はみんなで記念写真。また来年!!
***こどもアートスクールについて***
2017年09月20日
美術工芸系ブログ
***こどもアートスクールについて***
美術工芸系では、毎年8月に総社市内の小学生を対象にした「こどもアート
スクール」を開催しています。高校生が手助けしながら小学生に造形活動を体
験してもらう行事で、今年で5回目になります。今年はマーブリングやデカル
コマニなど、簡単な絵画技法を体験してもらう計画でした。
・・・しかし、今年はなぜか小学校を通じての参加申し込みがなく、こども
アートスクール開催の危機! そこで、当日までに参加の希望を直接連絡して
くれた3人の小学生と幼稚園児を招待して、規模は縮小しましたがなんとかこ
どもアートスクールを実施しました。
①デカルコマニ(合わせ絵)
折り目をつけた画用紙にチューブから絵の具をたらし、折りたたんでから広げ
てみると、不思議な絵柄が浮かび上がります。 蝶? 花? 一体何に見えるか
な? この技法は心理学のテストなどにも使われます。
②マーブリング(墨流し)
水面に絵の具をたらしてできる模様を紙に写し取ります。筆では描けない、流れ
るような模様は、繊細で魅力的です。
③スクラッチ(けずりだし)
明るい色のクレヨンを塗った上に、暗い色のクレヨンを塗りかぶせて、先が尖っ
たもので引っ掻くと、ネオンサインのように明るい色がキレイに出てきます。写真
の男の子は、今はまっているクワガタの対決を熱心に描いてくれました。
④カット(切り紙)
色紙を折りたたんではさみで切り込みを入れてから、丁寧に広げてみると・・・
雪の結晶のような模様ができあがります。七夕飾りやクリスマスツリーの飾りに使
えそうですね。
あっという間に2時間が経ちました。無心に絵画技法を試してくれている3人の
姿を見ると、描くことの楽しさの原点を再確認できたように思います。急遽3人の
補助をしてくれた高校生3人も、逆に彼らから学ぶことがあったことと思います。
参加してくれた皆さん、ありがとうございました。
理数系講演会が開かれました。
2016年07月12日
理数系講演会が開かれました。
平成28年7月11日 理数系講演会が開かれました。
講師の先生方は、「一般社団法人 エネルギー・環境理科教育推進研究所」からお越しくださいました、龍﨑 邦雄先生と松谷 信治先生です。

90分の時間枠いっぱいの盛りだくさんの内容に、理数系のみんなは一生懸命ついて行きました。放射線とは何か、放射能との違いは何かといったところから始まり、


霧箱の実験(放射線の飛跡を見る)、




はかるくんを使ってのベータ線の測定、放射線源と距離の関係を測定しグラフに描く実験、放射線の遮蔽効果の実験などを理数系の皆さんが実際に行いました。
霧箱の実験では、飛跡が見えると、「オー!!」という声が、あちらこちらとあがり感動の嵐でした。


その後も、福島原発事故の話から、チェルノブイリ原発の話、外部被曝、内部被曝と盛りだくさんで、最後に放射線の利用の演示実験がありました。プラスチックが放射線を当てることで、その形状を記憶するようになるとは、みんなも驚いていました。

« 前ページへ








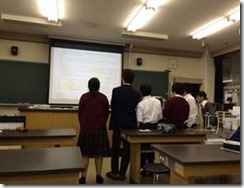
![clip_image002[4] clip_image002[4]](http://www.sojam.okayama-c.ed.jp/wordpress/wp-content/uploads/2018/11/clip_image0024.jpg)
![clip_image002[6] clip_image002[6]](http://www.sojam.okayama-c.ed.jp/wordpress/wp-content/uploads/2018/11/clip_image0026.jpg)